日本、台湾、中国、韓国など東アジアに広く分布する回遊魚。レプトセファルス(レプトケファルス)と呼ばれる特異的な幼生期を持ち、分類的にはウナギ目というグループに属する魚である。
ふ化後、北赤道海流に乗って西側に流れ、さらに北に向かう黒潮に乗り換えて日本沿岸に達することが分かっている。ふ化後の「仔魚」は移動の間に、母親由来の卵黄を栄養源にする「プレレプトセファルス」から、柳の葉のような形の「レプトセファルス」に変化し、日本沿岸にたどり着くころには稚魚「シラスウナギ」になって河川をさかのぼる。河川や湖などで5〜10年を過ごすうちに大きくなり、産卵のために再度、海に向かうと考えられている。
今まで詳しい生態などはわかっておらず、回遊している稚魚を捕獲して養殖していたが、2009年5月に東京大学大気海洋研究所などの研究チームが、マリアナ海溝付近の海域で世界で初めて、天然のニホンウナギの卵31個の採集に成功している。激減したウナギ資源の保全、管理や、養殖用稚魚の大量生産技術の開発につながると期待されている。
現在、日本にはニホンウナギとオオウナギの2種が自然分布し、鰻養殖の歴史は120年以上となる。また、外国産ウナギも養殖されている。2009年の日本におけるウナギの年間消費量は約7万トンで、約5万トンは中国や台湾からの輸入で賄われている。
目次
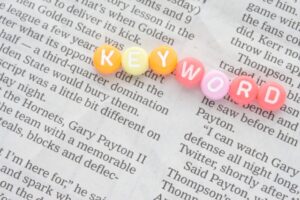
コメント