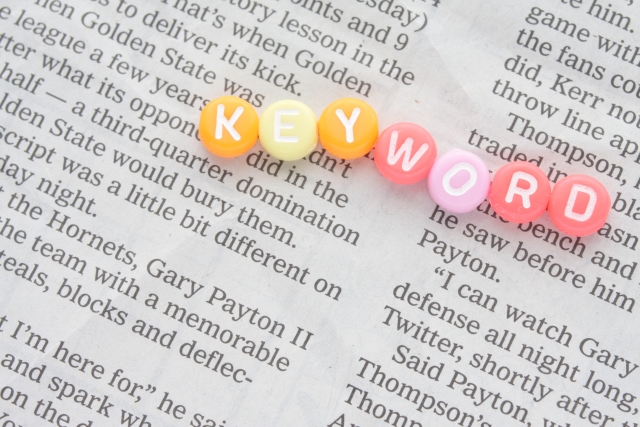ビジネス– category –
-

通信自由化
1984年の中曽根内閣時に、国有事業だった通信事業を民営化したこと。国内通信事業を独占していた電電公社と、国際通信事業を独占していた国際電電(KDD)をそれぞれ民営化するとともに、他の事業者が通信事業に参入することを促がしている。その際、電電公社... -

農業生産法人
一定の条件のもとで農地の所有を認められた法人のこと。株式会社や有限会社、合資会社などの形態をとる場合もある。農業生産法人としての条件は、主な事業が農業か農業に関連する事業であること、農業者や農業関係者の議決権が4分の3以上であること、役員... -

逃避先通貨
金融市場で発生したリスクを避けるために買われる、比較的リスクが低い通貨のこと。買われた逃避先通貨は価格が上昇する。かつては米ドルが逃避先通貨として長らく選ばれてきたが、2008年のリーマンショック以降の米国経済の停滞でドルへの信頼が揺らいだ... -

通信規制
インターネットなどの通信が混雑することを避けるため、通信に一定の制限を設けること。インターネットでファイル交換ャtトなどを用いて、大容量の動画ファイルや音楽ファイルなどをダウンロードするユーザーが増えたことで、ネット渋滞と呼ばれる現象が起... -

農民工
中国において、戸籍は農村だが農業に従事せず、都市部へ出稼ぎに出て被雇用者として働く人のこと。 1978年、中華人民共和国が市場経済を導入すると、沿岸部の工業が発展した。それに対して、特に貧困地帯である内陸部の人々が沿岸部へ職を求めて移動をした... -

逆三尊【三尊底】
株式や為替相場のチャートパターンのひとつで、3回にわたって安値を付け、そのうちの真ん中が最も安値になっている形のこと。逆三尊の形が現れると、相場は下降トレンドから上昇トレンドに転じたと見ることができる。3つ目の谷が最も低い2つ目の谷よりも下... -

通信費
郵便料金や電話料金などの総称。従来は営業費用全体に占める割合は小さかったが、最近はインターネットなどの普及により、インターネット接続料金やサーバー使用料、企業ホームページなどのドメイン登録料なども含まれるため、とくにIT企業においては占... -

辺野古
沖縄県名護市内にある地域で、米軍基地であるキャンプシュワブがある。沖縄本島の中央東側に位置している。キャンプシュワブは、普天間基地移設の候補地となっている。普天間基地の移設問題をめぐっては、2006年に自民党政権によって在日米軍再編ロードマ... -

逆乖離
パリティ価格よりも転換社債の時価の方が割安な状態のこと。パリティ価格とは、転換社債を株式に転換した際の価値を示す理論価格で、株価を転換価額で除して、100を掛けた価格として算定される。理論上の価格であるパリティ価格は、通常、現実の転換社債の... -

通勤定期乗車券【通勤定期券】
公共交通機関で、通勤などのために一定期間、一定区間が何回でも乗車可狽ネ定期乗車券のこと。普通乗車券で、有効期間内に毎日1往復する料金の合計よりも低価格に設定されており、通勤証明書などを提示する必要はなく、誰でも購入することができる。ICカー...