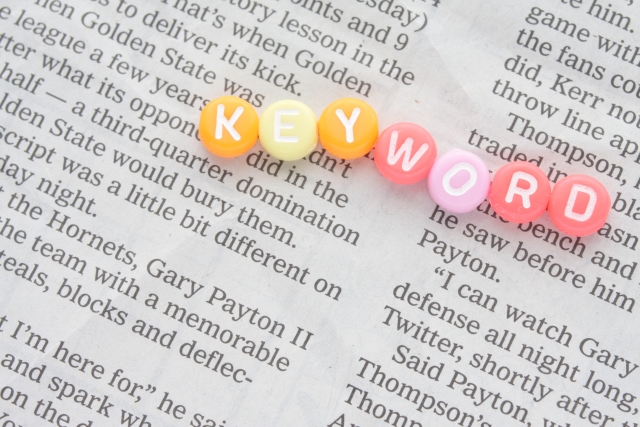gigmaster– Author –
-

通信費
郵便料金や電話料金などの総称。従来は営業費用全体に占める割合は小さかったが、最近はインターネットなどの普及により、インターネット接続料金やサーバー使用料、企業ホームページなどのドメイン登録料なども含まれるため、とくにIT企業においては占... -

通信自由化
1984年の中曽根内閣時に、国有事業だった通信事業を民営化したこと。国内通信事業を独占していた電電公社と、国際通信事業を独占していた国際電電(KDD)をそれぞれ民営化するとともに、他の事業者が通信事業に参入することを促がしている。その際、電電公社... -

逆輸入
日本企業が海外を拠点として生産した製品を、日本国内に輸入して販売すること。現地の低賃金による生産コストの削減が主な目的である。そのため企業は、海外の現地子会社で生産したほうがコストを削減できる場合には、生産拠点を海外へ移すことがある。ま... -

通商政策局
経済産業省の組織の一つで、通商に関する政策や協定、手続に関することや、通商経済上の国際協力に関する政策の企画などを行う。日本経済の競争力強化とともに、大国の一つとして世界経済の発展に貢献するべく、対外経済政策の戦略的展開を目指している。... -

通信規制
インターネットなどの通信が混雑することを避けるため、通信に一定の制限を設けること。インターネットでファイル交換ャtトなどを用いて、大容量の動画ファイルや音楽ファイルなどをダウンロードするユーザーが増えたことで、ネット渋滞と呼ばれる現象が起... -

通商産業省【通産省】
経済産業省の前身となった中央省庁。2001年の中央省庁改編により、通商産業省は廃止され、全ての機狽ヘ経済産業省に引き継がれた。通商産業省は1949年に商工省が外局である貿易庁、石炭庁と統合して発足して以来、産業政策、通商、貿易、科学技術開発、特許... -

逆進性
ある目的を果たすためにしたことが、実質的に目的とは反対の効果があがってしまうこと。代蕪Iなものとして消費税の逆進性があげられる。消費税は所得の高さに関わらず、全ての人に課税するものであるため、家計に占める生活必需品などの割合が高い低額所得... -

通信の秘密
日本国憲法や電気通信事業法によって、電話や電子メールでの通信内容や通信事実の情報が保護されていること。保護されているのは通信の有無、通信の内容、通信の告ャ要素の3種類となっている。通信の告ャ要素とは、通信した時間、通信したユーザーなどの情報... -

退職給与
法人税法上では明確な定義はないが、退職を起因として支給される一切の給与のことを意味する。また、法人税法上では、退職所得には該当しない退職年金なども退職給与としてとり扱われることになる。また、現物支給ということもあり、例えば、役員が在任中... -

途中償還
債券の発行者が満期前に発行額の一部または全額を所有者へ支払い、その債券を消滅させること。償還には他に、満期日に行われる「満期償還」がある。途中償還はその方法により、定期的に発行額の一定割合を償還する「定時償還」と発行者の意思によって償...