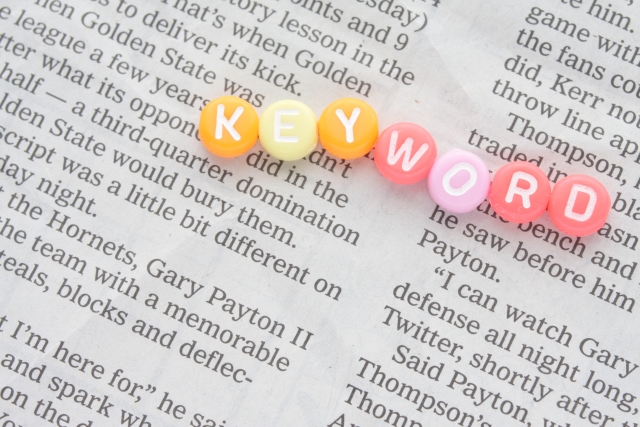ビジネス– category –
-

経常利益率
売上高に対する経常利益の比率。経常利益÷売上高×100(%)の計算式で浮ウれる。この指標から、企業が企業活動全体でどれだけ効率的に利益を出したのかが見られる。売上高とは企業が製品や商品、あるいはサービスを販売、提供した対価として顧客から受け取った... -

組閣
内閣総理大臣が内閣を組織すること。総理大臣は、はじめに内閣官房長官を任命する。そして総理大臣、内閣官房長官、与党代侮メにより組閣本部がつくられる。その後、閣僚の名簿が確定すると就任嵐闔メが呼ばれ、総理大臣により国務大臣に任命される。内閣の... -

経常収支
国際収支の中核で、次の4つの経常取引の収支の総称のこと。輸出入の集計である「貿易収支」、日本企業が外国で得た収益から外国企業が日本国内で得た収益を引いた額である「所得収支」、対価をともなわない開発途上国への経済援助や国際機関への拠出金の... -

経営コンサルタント
経営戦略・生産効率・組織改革など企業経営全般に関する問題を、調査や分析をすることによって解決策を見つけ指導を行う専門家のこと。最近ではリスクマネジメントや環境問題などの対応業務も増えているといわれており、日々の経済の動きや法改正、新技術... -

経済三団体
日本経済団体連合会(日本経団連)、日本商工会議所(日商)、経済同友会の3団体のこと。まず「日本経団連」は東証一部上場の大企業が中心に会員となっている団体のことである。組織が結成された目的は、日本の経済政策に対する財界からの提言と発言力の確保に... -

経営セーフティ共済【中小企業倒産防止共済制度】
中小企業が、取引先企業の倒産の影響を受けて倒産する等の事態が発生を防止するための共催制度のこと。中小企業者の相互扶助の精神に基づき、中小企業の拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的として、中... -

経済協力開発機香@【OECD】
OECDとはOrganisation for Economic Co-operation and Developmentの略で、経済協力開発機高フこと。国際経済全般を取り扱い協議する国際機関である。本部はフランスのパリに設置されている。第二次大戦後、1948年に米国のマーシャル国務長官が、混乱状態... -

累進課税 【progressive taxation】
収入が多いほど税率を大きくする制度。所得税や相続税、贈与税などで用いられている。所得税の場合、所得金額が330万円以下であれば10%(控除額0円)、330万円超〜900万円以下であれば20%(同33万円)、900万円超〜1 -

経営体 【management entity】
経営体とは単に企業のみを意味するものではなく、経済的な事業を営む組織体であるとともに、社会が求める財・サービスを効果的かつ効率的に生産することを役割として持っている組織体のことである。この社会的役割を適切に果たすためには、生産活動に投... -

経済同友会【同友会】
1946年に日本経済の堅実な再建のために、中堅企業の経営者有志83名が集まり誕生した経済団体のこと。経済社会の様々な問題について自由に議論し、その見解を社会に対して提言することを目的とする。企業の経営者が個人の資格で会員となり加入し、個々の企...